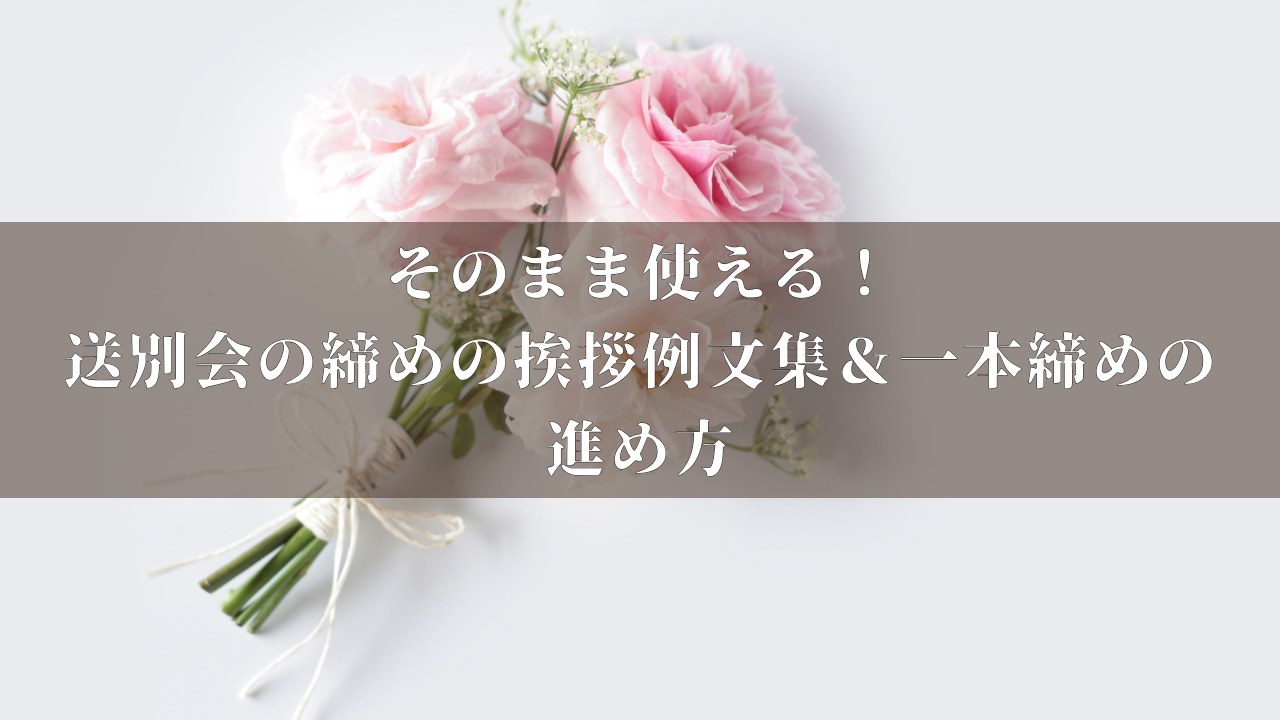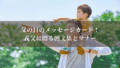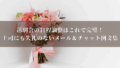送別会の最後をどんな言葉で締めるかによって、その日の雰囲気は大きく変わります。
「締めの挨拶」と「一本締め」は、主役に感謝を伝えると同時に、参加者全員が前向きな気持ちで帰れるようにする大切な役割を担っています。
とはいえ、いざ任されると「何を言えばいいのか分からない」「進行の仕方を間違えたくない」と不安になる人も多いですよね。
この記事では、送別会で使える締めの挨拶を上司・同僚・幹事といった立場別に豊富な例文で紹介します。
さらに、そのまま読み上げられるフルバージョン例文や、一本締め・一丁締め・三本締めの進め方も整理しました。
最新のオンライン送別会や少人数の場合に使えるアイデアも加えています。
この記事を読めば、どんな場面でも安心して締めの役を務められるようになります。
送別会の締めを成功させる基本ポイント
送別会の最後をどう締めるかによって、全体の印象は大きく変わります。
ここでは、締めの挨拶や一本締めを成功させるための基本ポイントを整理して解説します。
「なぜ締めが大事なのか?」を理解することで、安心してその場をまとめられるようになります。
締めの挨拶が持つ意味と役割
締めの挨拶は、会の終了を告げると同時に、主役への感謝や参加者への労いを伝える大切な役割を持ちます。
場の雰囲気を整え、全員が心地よく帰れるようにするために欠かせない要素といえます。
ここで一言添えるだけで、主役や参加者に「いい時間だった」と思ってもらえる余韻が残ります。
一本締め・一丁締め・三本締めの違い
締めといえば「手を打つ動作」が欠かせませんが、その種類はいくつかあります。
混同されがちなので、ここで整理しておきましょう。
| 種類 | 方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 一本締め | 3×3+1で10回手を打つ | 正式感があり、会をしっかり締めたい時に使う |
| 一丁締め | 「パン!」と1回だけ手を打つ | 最も簡単で場をすっきり終えられる |
| 三本締め | 一本締めを3回繰り返す | 大規模で厳かな場に適している |
送別会では、一本締めか一丁締めを選ぶのが一般的です。
三本締めは、特別に格式を重んじる場で用いられることが多いですね。
失敗しないための基本マナー
締めを担当する人が気をつけるべきなのは、段取りを事前に確認しておくことです。
「いつ締めを行うか」「誰が進行役か」を共有しておくだけで、流れがスムーズになります。
また、声の大きさや言葉遣いを少し意識するだけで、場全体が心地よくまとまります。
逆に、長すぎる挨拶や過度にくだけた進行は、雰囲気を崩す原因になりかねません。
短く・明るく・前向きにが鉄則です。
送別会の締めの挨拶の基本構成
いざ締めの挨拶を任されると、何から話せばいいのか迷いますよね。
実は、挨拶には「型」があり、それに沿えば誰でも安心してまとめられます。
ここでは、送別会の挨拶を組み立てるときの基本的な流れを紹介します。
感謝を伝えるフレーズの型
最初に話すべきは、参加者への感謝です。
いきなり本題に入るよりも、「今日は集まってくれてありがとう」と伝えることで場が温かくなります。
| 場面 | 例文 |
|---|---|
| 全体への感謝 | 「本日はお集まりいただき、ありがとうございます。」 |
| 主役への感謝 | 「〇〇さん、これまで本当にありがとうございました。」 |
一言でも「ありがとう」を入れるだけで雰囲気が和らぎます。
主役を讃えるフレーズの型
次は、主役に向けた言葉です。
これが挨拶の中心になる部分で、相手の功績や人柄を讃えると良いでしょう。
| 内容 | 例文 |
|---|---|
| 功績を讃える | 「〇〇さんのおかげで、私たちは安心して仕事に取り組めました。」 |
| 未来を応援する | 「新しい環境でも、〇〇さんらしく輝かれることを心から願っています。」 |
過度に感情的にならず、前向きな言葉でまとめるのがポイントです。
会を締める流れを示すフレーズの型
最後は「これで終わりますよ」と伝える部分です。
名残惜しい雰囲気を残しつつ、自然に終わりへ導きましょう。
| 状況 | 例文 |
|---|---|
| 終了を予告する | 「そろそろお開きとさせていただきます。」 |
| 一本締めを促す | 「最後に一本締めで締めたいと思います。」 |
このように「感謝 → 主役を讃える → 終了を示す」という流れを踏めば、自然で心地よい締めができます。
挨拶は1〜2分に収めるのが理想です。
【立場別】送別会の締めの挨拶例文集(ショート&フルバージョン)
実際にその場で使える例文を、立場ごとにまとめました。
短く一言で済ませたい人向けの「ショートバージョン」と、そのまま読み上げられる「フルバージョン」を用意しています。
シーンに合わせて選んでみてください。
上司が行う締めの挨拶
上司の場合は、感謝と労いをしっかり伝えることが大切です。
| バージョン | 例文 |
|---|---|
| ショート | 「〇〇さん、長い間本当にありがとうございました。今後のご活躍を心から願っています。それでは一本締めで締めたいと思います。」 |
| フル | 「皆さん、本日はお集まりいただきありがとうございます。〇〇さんはこれまでチームの中心として、私たちを支えてくださいました。 そのおかげで、困難な場面でも安心して前に進むことができました。 〇〇さんの次のステージでのご活躍を、心からお祈りしております。 それでは、この会をお開きとし、最後に一本締めで締めさせていただきます。皆さま、ご協力をお願いします。」 |
上司の挨拶は、落ち着いたトーンとフォーマルさがポイントです。
同僚・後輩が行う締めの挨拶
同僚や後輩の場合は、距離の近さを活かして、明るくカジュアルにまとめましょう。
| バージョン | 例文 |
|---|---|
| ショート | 「〇〇さん、本当にお世話になりました。またいつかご一緒できる日を楽しみにしています。それでは一本締めで締めたいと思います。」 |
| フル | 「〇〇さん、これまで本当にありがとうございました。 一緒に仕事をする中で学ぶことが多く、感謝の気持ちでいっぱいです。 これからの新しい環境でも、〇〇さんらしく前向きに歩んでいかれると思います。 また近いうちにお会いできることを楽しみにしています。 それでは最後に一本締めで、この場を締めさせていただきます。皆さん、ご唱和をお願いします。」 |
幹事が行う締めの挨拶
幹事の場合は、場を円滑に締めることを意識しましょう。
| バージョン | 例文 |
|---|---|
| ショート | 「皆さん、本日はありがとうございました。最後に一本締めで締めたいと思います。ご協力をお願いします。」 |
| フル | 「本日は〇〇さんの送別会にご参加いただき、ありがとうございました。 皆さまのおかげで、とても温かい時間を過ごすことができました。 〇〇さんも楽しんでいただけたのではないかと思います。 それでは名残惜しいですが、この会をお開きとし、最後に一本締めで締めたいと思います。 皆さま、ご起立をお願いいたします。」 |
シンプルにまとめたい人向け一言例文集
あまり長く話したくないときや、気軽な場面では一言で十分です。
- 「〇〇さん、ありがとうございました。一本締めで締めたいと思います。」
- 「皆さん、お疲れさまでした。それでは一本締めをお願いします。」
- 「これからのご活躍を願って、一本締めで終わりにしましょう。」
短い挨拶でも、声のトーンや笑顔で温かさを伝えることが大切です。
一本締めの正しいやり方と進行例
送別会の締めといえば「一本締め」が最もよく使われます。
進行の仕方を間違えなければ、会全体をスッキリと終わらせられます。
ここでは、一本締めの基本手順と実際の進行例を紹介します。
基本の進行手順と掛け声
一本締めには、決まった手順があります。
誰が進行役になっても迷わないように、流れを覚えておきましょう。
| 手順 | 進行役の声かけ |
|---|---|
| ① 締めを宣言 | 「では、〇〇さんの今後のご活躍を祈って、一本締めで締めたいと思います。」 |
| ② 全員に準備を促す | 「皆さま、ご起立をお願いします。」 |
| ③ 掛け声 | 「ではいきます。よーっ!」 |
| ④ 全員で手を打つ | 「パン!」(全員で一斉に) |
全員が同じタイミングで手を打つ一体感こそが一本締めの魅力です。
そのまま使える「進行スクリプト例」
進行役が迷わないように、実際のスクリプトを用意しました。
そのまま読み上げても自然に進行できます。
- 「それでは、名残惜しいですがこの会をお開きといたします。」
- 「最後に、〇〇さんの新たな門出を祝って、一本締めで締めたいと思います。」
- 「皆さま、ご起立ください。」
- 「では、よーっ!」
- (全員で「パン!」と手を打つ)
声が小さいと合図が伝わらないため、はっきりと声を出すことが大切です。
一丁締め・三本締めの実例と場面別活用法
一本締め以外にも「一丁締め」や「三本締め」があります。
それぞれ使う場面が違うので、覚えておくと便利です。
| 種類 | 方法 | 活用シーン |
|---|---|---|
| 一丁締め | 「パン!」と1回だけ手を打つ | 少人数の集まりやカジュアルな雰囲気に最適 |
| 一本締め | 3×3+1の10回手を打つ | 送別会など、多人数でしっかり締めたいときにおすすめ |
| 三本締め | 一本締めを3回繰り返す | 大規模な会や、特にフォーマルな場で使用 |
会の雰囲気に合わせて締め方を選ぶと、自然で心地よい印象を残せます。
最新の送別会に合わせた締め方のアイデア
近年は働き方の多様化に伴い、送別会の形も変化しています。
オンラインでの開催や、少人数での集まりなど、従来とは違う場面も増えてきました。
ここでは、それぞれの状況に合わせた締め方の工夫を紹介します。
オンライン送別会での締めの挨拶例文
画面越しでも一体感を演出することがポイントです。
手を打つ代わりに拍手や掛け声を合わせると、自然に盛り上がります。
| シーン | 例文 |
|---|---|
| 拍手で締める | 「それでは最後に、画面に向かって拍手をお願いします。せーの、ありがとうございました。」 |
| 掛け声で締める | 「皆さんご一緒に、せーの! お疲れさまでした。」 |
オンラインでは声や動作をそろえることで、一体感を作り出せます。
少人数の送別会での締めの挨拶例文
少人数の場合は、堅苦しくせず、自然体の挨拶が好まれます。
あえて一言で締めても、距離が近いため温かさが伝わります。
- 「〇〇さん、これからも応援しています。それでは皆さんで拍手をお願いします。」
- 「今日は集まってくださりありがとうございました。最後に軽く拍手で締めたいと思います。」
小規模だからこそ、過度に形式張らず、フランクにまとめると好印象です。
ユーモアや笑いを交えた締めの工夫例
場を和ませたいときには、少しユーモアを取り入れるのも良い方法です。
ただし、主役や参加者の性格に合った表現を選ぶことが大切です。
| 工夫 | 例文 |
|---|---|
| 軽いジョークを交える | 「〇〇さんがいなくなると寂しくなりますが、連絡が来るまでこちらから押しかけるかもしれません。それでは一本締めで締めましょう。」 |
| 未来を笑いでつなげる | 「次に集まるときは、さらに成長した〇〇さんにご挨拶してもらいましょう。それでは最後に一本締めをお願いします。」 |
ユーモアはほんの一言で十分です。
主役を立てつつ場を和ませれば、温かく記憶に残る締めになります。
最新の送別会に合わせた締め方のアイデア
近年は働き方の多様化に伴い、送別会の形も変化しています。
オンラインでの開催や、少人数での集まりなど、従来とは違う場面も増えてきました。
ここでは、それぞれの状況に合わせた締め方の工夫を紹介します。
オンライン送別会での締めの挨拶例文
画面越しでも一体感を演出することがポイントです。
手を打つ代わりに拍手や掛け声を合わせると、自然に盛り上がります。
| シーン | 例文 |
|---|---|
| 拍手で締める | 「それでは最後に、画面に向かって拍手をお願いします。せーの、ありがとうございました。」 |
| 掛け声で締める | 「皆さんご一緒に、せーの! お疲れさまでした。」 |
オンラインでは声や動作をそろえることで、一体感を作り出せます。
少人数の送別会での締めの挨拶例文
少人数の場合は、堅苦しくせず、自然体の挨拶が好まれます。
あえて一言で締めても、距離が近いため温かさが伝わります。
- 「〇〇さん、これからも応援しています。それでは皆さんで拍手をお願いします。」
- 「今日は集まってくださりありがとうございました。最後に軽く拍手で締めたいと思います。」
小規模だからこそ、過度に形式張らず、フランクにまとめると好印象です。
ユーモアや笑いを交えた締めの工夫例
場を和ませたいときには、少しユーモアを取り入れるのも良い方法です。
ただし、主役や参加者の性格に合った表現を選ぶことが大切です。
| 工夫 | 例文 |
|---|---|
| 軽いジョークを交える | 「〇〇さんがいなくなると寂しくなりますが、連絡が来るまでこちらから押しかけるかもしれません。それでは一本締めで締めましょう。」 |
| 未来を笑いでつなげる | 「次に集まるときは、さらに成長した〇〇さんにご挨拶してもらいましょう。それでは最後に一本締めをお願いします。」 |
ユーモアはほんの一言で十分です。
主役を立てつつ場を和ませれば、温かく記憶に残る締めになります。
まとめ:送別会を心に残る形で締めくくろう
送別会の最後をどう締めるかで、その日の印象は大きく変わります。
挨拶や一本締めは単なる儀式ではなく、参加者全員の気持ちを前向きにつなぐ大切な時間です。
ここで紹介した流れや例文を活用すれば、自信を持って場をまとめられるはずです。
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| 基本の流れ | 感謝 → 主役を讃える → 終了を告げる |
| 挨拶の長さ | 1〜2分以内にまとめる |
| 締め方の選び方 | 雰囲気に合わせて一本締め・一丁締めを選択 |
| 安心の工夫 | メモやフレーズを準備しておく |
最後に大切なのは「心を込めて伝えること」です。
上手に話すことより、誠実に気持ちを伝えることの方が印象に残ります。
送別会を締めくくるその一言が、主役にとっても参加者にとっても温かい記憶となるでしょう。