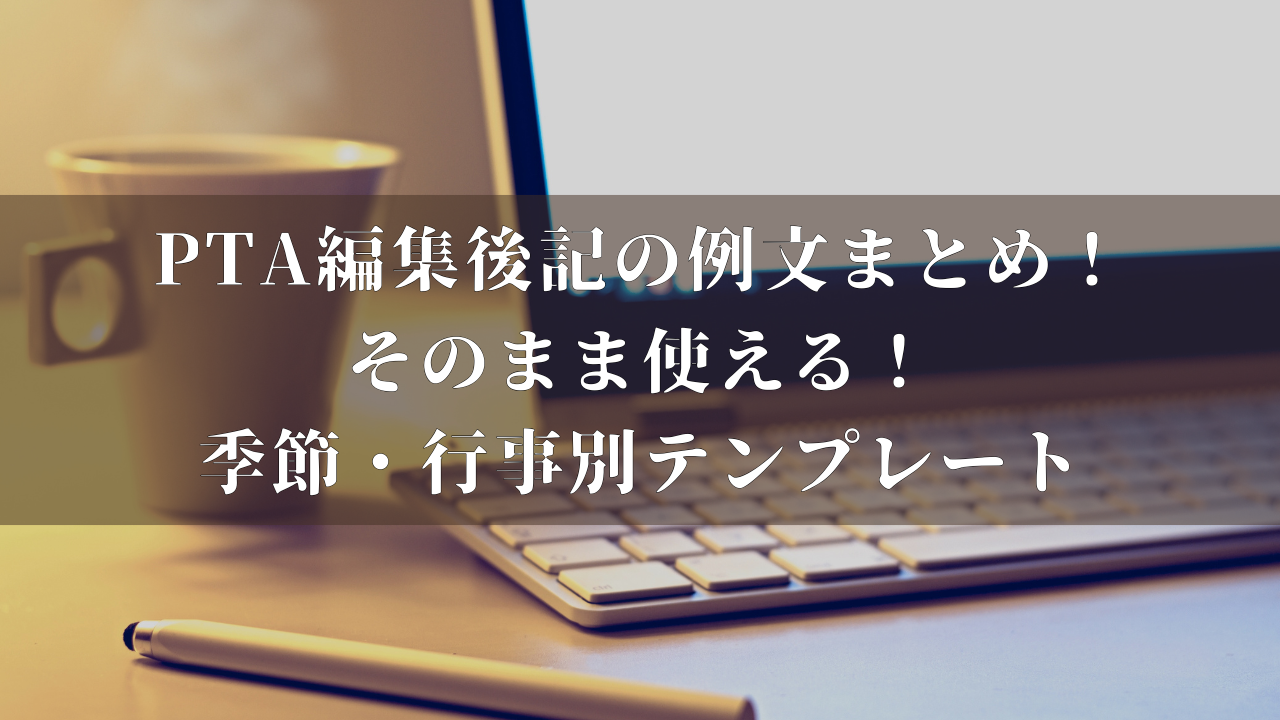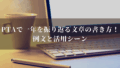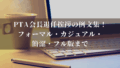「編集後記って、何を書けばいいの?」と迷っていませんか?
PTA広報誌の最後を飾る編集後記は、制作の裏側や思いを伝える大切なパート。
でも実際には、文章に苦手意識があったり、毎回ネタに困ってしまったりする方も多いですよね。
この記事では、編集後記の基本構成から、季節・行事別に使える書き出し文例、丸ごと使えるフル例文まで徹底的にご紹介。
さらに、ついやりがちなNGパターンや、読まれる編集後記にするための工夫も掲載しています。
初めて広報委員を担当する方も、毎年同じ文になってしまうとお悩みの方も、この記事を読めばきっとヒントが見つかるはずです。
読者に伝わる、あなたらしい編集後記づくりを一緒に目指しましょう。
PTA広報誌の編集後記とは?役割と意味
この章では、PTA広報誌における「編集後記」が果たす役割と、その意味について解説します。
読み物の締めくくりとして軽く扱われがちですが、実は編集後記こそが読者との心の距離を縮める“架け橋”なのです。
なぜ編集後記が大切なのか
編集後記は、記事本文には書ききれない思いや、制作の裏側を伝える「自由なひとことコーナー」です。
固いトーンになりがちな広報誌の中で、唯一、個人の言葉で語ることが許される場所とも言えます。
たとえば「保護者インタビューの途中で、子どもたちが突然歌い出して場が和みました」といった裏話を添えるだけで、紙面に温かみが生まれますよね。
| 編集後記の役割 | 具体的な効果 |
|---|---|
| 制作者の思いを伝える | 読者との信頼関係を築ける |
| 記事に出てこない裏話を紹介 | 紙面に“人間味”が出る |
| 親しみやすさを演出 | 次号への関心を高める |
読者に伝えたい本当のメッセージとは
PTA広報誌は、行事報告や活動内容の紹介が中心になりがちです。
しかし、編集後記では「この学校で過ごす日々は、こんなにも温かく、楽しいものなんです」というメッセージを、直接的に届けることができます。
一方的に情報を届けるだけでなく、「一緒にこの場を作っていきましょう」という気持ちを添えることで、読者の心にぐっと届く文章になるのです。
読み手に寄り添うひと言。それが、編集後記の本質です。
次の章では、そんな編集後記をスムーズに書けるようになる「基本構成」と「書き方のコツ」をお伝えします。
PTA編集後記の基本構成と書き方ステップ
編集後記を書くのは初めてという方でも大丈夫。
この章では、誰でも安心して書けるようになる「3ステップ構成」と、自然な文章に仕上げるためのポイントをご紹介します。
書き出しのポイント(あいさつ・季節感)
最初の一文は読者へのあいさつや季節のひとことから始めましょう。
いきなり内容に入るよりも、温かみが感じられて読みやすくなります。
たとえば、こんな書き方が使えます。
| 季節 | 書き出し例 |
|---|---|
| 春 | 「春のやわらかな風に、新しい季節の始まりを感じます。」 |
| 夏 | 「暑さが本格的になってきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。」 |
| 秋 | 「落ち葉の色づきに、季節の移り変わりを感じる頃となりました。」 |
| 冬 | 「冷たい風に冬の訪れを感じる今日この頃です。」 |
本文の流れ(内容紹介・裏話・感謝)
中盤では、広報誌の特集や取材で印象に残った出来事を中心に書きます。
裏話や制作エピソードがあると、読者も「そんなことがあったんだ!」と興味を持ちやすくなります。
感謝の言葉も添えると、読者との距離がぐっと近づきます。
例:
「今回の運動会特集では、カメラ越しに子どもたちの笑顔をたくさん捉えることができました。
保護者の皆さまのご協力に心より感謝申し上げます。」
締めくくりのコツ(お願い・次号予告など)
最後は読者とのつながりを意識した言葉でまとめるのがコツです。
「次号もお楽しみに」「引き続き応援よろしくお願いします」など、少し前向きな言葉を添えましょう。
この部分で読者に“また読みたい”と思わせる余韻を残せれば、完璧です。
| タイプ | 締めの一文の例 |
|---|---|
| 感謝で締める | 「皆さまのご協力に心から感謝いたします。」 |
| つながりを意識 | 「今後もこの広報誌を通じて交流が続けば嬉しいです。」 |
| 次号の予告 | 「次号もどうぞお楽しみにしてくださいね。」 |
次章では、こうしたステップを踏まえたうえで、すぐに使える「書き出し例」をテーマ別にご紹介します。
編集後記に使える定番の書き出し文例
ここでは、PTA広報誌の編集後記で使いやすい「書き出しのひと言」をテーマ別にご紹介します。
迷ったときにそのまま使える文例ばかりなので、テンプレートとしても活用できますよ。
感謝を伝えるパターン
読者や協力者への感謝から始めると、広報誌全体の印象がとても柔らかくなります。
特に、定期的に読んでくれている保護者や先生方に向けたひと言が効果的です。
| 文例 |
|---|
| 「いつもPTA広報誌をご覧いただきありがとうございます。」 |
| 「保護者の皆さまのご協力のもと、今号も無事に完成いたしました。」 |
| 「取材にご協力いただいた皆さまに、心より感謝申し上げます。」 |
季節を取り入れるパターン
季節のあいさつは、編集後記に自然なリズムを生み出します。
時期に応じて、読者と同じ季節感を共有することで、親近感が高まります。
| 季節 | 書き出し文例 |
|---|---|
| 春 | 「春のやさしい風が心地よい季節となりました。」 |
| 夏 | 「日差しが強くなり、夏の訪れを感じるようになりましたね。」 |
| 秋 | 「紅葉の便りが届く季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。」 |
| 冬 | 「寒さが増し、冬の訪れを感じる今日この頃です。」 |
イベントや行事に合わせたパターン
号の内容に合わせて書き出すと、読者の関心を引きやすくなります。
運動会、文化祭、卒業式など、イベントの余韻を活かしましょう。
| 行事 | 書き出し文例 |
|---|---|
| 運動会 | 「子どもたちの元気な姿がまぶしい運動会が無事に開催されました。」 |
| 文化祭 | 「文化祭で見せた子どもたちのアイデアと笑顔に、心が温まりました。」 |
| 卒業 | 「卒業という新たな門出を迎えた子どもたちの背中に、エールを送ります。」 |
次の章では、実際の誌面で使える「フルバージョンの例文テンプレート」をたっぷりご紹介します。
すぐ使える!PTA編集後記の例文テンプレート
ここでは、さまざまなシーンに応じて使える「フルバージョンの編集後記例文」をご紹介します。
どれも100〜200文字前後でまとめられており、そのまま使うことも、自分用にアレンジすることも可能です。
新年度スタート用の例文
新しいメンバーや学年が始まるタイミングは、読者も前向きな気持ちになっている時期。
爽やかな印象の文章がぴったりです。
| 例文 |
|---|
| 「新年度を迎え、今年も広報誌の制作がスタートしました。新たに加わった仲間とともに、子どもたちの姿を温かく見守りながら、楽しく制作していきたいと思います。今号もご覧いただきありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。」 |
| 「春の陽気の中、新しいクラスや学年での生活が始まりました。新メンバーでの広報活動も始動し、初取材では笑顔あふれる子どもたちの様子をお届けできました。ぜひ、ゆっくりお楽しみください。」 |
運動会・文化祭特集号の例文
大きなイベントの後は、その熱気や感動を共有できる文章が好まれます。
現場の空気感を伝えるように意識してみましょう。
| 例文 |
|---|
| 「今回の特集では、先日行われた運動会の様子をお届けしました。当日は青空の下、全力で駆け抜ける子どもたちの姿に胸が熱くなりました。撮影や取材にご協力いただいた保護者の皆さま、本当にありがとうございました。」 |
| 「文化祭での子どもたちの自由な発想や笑顔がとても印象的でした。取材では“この作品、どうやって作ったの?”とたくさん質問する楽しさもありました。ご協力いただいた先生方に感謝を込めて、今号をお届けします。」 |
卒業・年度末号に最適な例文
少しセンチメンタルな時期ですが、前向きなメッセージで締めくくると、読後感が良くなります。
感謝と未来へのエールがキーワードです。
| 例文 |
|---|
| 「1年間の活動を通じて、子どもたちの成長を感じる場面がたくさんありました。卒業を迎える皆さんの新しい旅立ちが、希望に満ちたものになりますよう心から願っています。今年も広報誌をご覧いただきありがとうございました。」 |
| 「年度末の締めくくりとして、思い出深い場面を振り返る特集号をお届けします。取材を通して感じたのは、日々の学校生活の中にある何気ない温かさでした。1年間、本当にありがとうございました。」 |
次の章では、読者に「読みにくい」と感じさせてしまうNGパターンを解説します。
やってはいけないNG編集後記とは?
ここでは、編集後記でついやってしまいがちなNGパターンをご紹介します。
心を込めて書いたつもりでも、読者に違和感やストレスを与えてしまう可能性も。
“ありがちな落とし穴”を知っておくことで、より伝わる文章が書けるようになります。
ネガティブすぎる内容
気持ちが入りすぎるあまり、「大変でした」「間に合いませんでした」といったマイナス表現ばかりになるのはNGです。
苦労話を少し入れるのは問題ありませんが、全体のトーンが重くならないように注意しましょう。
| NG例 | 改善案 |
|---|---|
| 「時間がなく、ギリギリの編集でした」 | 「限られた時間の中でも、工夫して制作に取り組みました」 |
| 「正直、疲れました…」 | 「大変でしたが、今号も無事に完成し、達成感があります」 |
読者が共感しづらい自己満表現
編集後記は「自分のメモ」ではなく、「読者との共有スペース」です。
内部の事情や内輪ネタだけで終始してしまうと、読み手には伝わらず“他人事感”が残ってしまいます。
| NG例 | 改善案 |
|---|---|
| 「○○さんが全部やってくれました」 | 「委員全員で協力して、無事に完成しました」 |
| 「○○小の取材はいつも楽しいです」 | 「今回も、子どもたちの笑顔に元気をもらいました」 |
冗長で読みにくい文章
文章が長すぎたり、同じ語尾が続いたりすると、読者が読み疲れてしまいます。
1文1テーマ・1文1メッセージを意識して、簡潔にまとめましょう。
| NG例 | 改善案 |
|---|---|
| 「子どもたちが頑張っていたのがとても素敵で、嬉しくて、私も励まされました」 | 「子どもたちの頑張りに、私も元気をもらいました」 |
| 「○○という取材内容があって、それについてこんな風に感じました」 | 「○○の取材を通して、新たな一面に触れることができました」 |
次の章では、読者にとって“読みやすく心に残る編集後記”にするための5つの工夫をご紹介します。
読まれる編集後記にする5つの工夫
編集後記をただ「書く」だけでなく、「読んでもらえる」文章にするにはちょっとした工夫が必要です。
この章では、広報初心者でもすぐ実践できる、読み手の心に残る編集後記の作り方を5つの視点から紹介します。
短くても心に残る言葉選び
長い文章よりも、ひとつの印象的な言葉のほうが読者の記憶に残ります。
たとえば「笑顔に救われた」「何気ない一言が心に残った」など、シンプルでも共感できる言葉を意識しましょう。
| 印象に残る言葉 | 置き換え例 |
|---|---|
| 「成長を感じました」 | 「背中が少しだけ大きく見えました」 |
| 「楽しい取材でした」 | 「カメラを構える手が止まらないほど、夢中でした」 |
読みやすさを意識したフォーマット
スマホでも読みやすいように、1文は短く、改行を多めに。
特に編集後記は文字量が限られているので、「詰め込みすぎ」は禁物です。
語尾も「〜ました」「〜です」「〜ます」などをバランスよく使い分けると、読みやすさが増します。
読者との“共通点”を盛り込む
「子どもたちの成長が早くて驚きますよね」など、読者と“同じ立場”を感じさせる言葉を入れると、共感されやすくなります。
読者の多くが保護者であることを意識し、自分ごととして受け取ってもらえる内容を目指しましょう。
比喩やイメージを活用する
「まるで映画のワンシーンのようでした」「手のひらサイズの努力」など、ちょっとした比喩や描写を入れると、印象的な編集後記になります。
子どもたちの様子を伝える場面で特に効果的です。
広報委員“らしさ”をにじませる
広報委員としての目線や気づきを一言入れることで、記事全体に一体感が生まれます。
たとえば「裏方の立場で見た運動会は、また違った感動がありました」など、制作者だからこその視点を加えてみましょう。
次章では、この記事全体をまとめながら、編集後記というコーナーの本質にもう一度迫ります。
まとめ:編集後記でPTA広報誌に“人間味”を
ここまで、PTA広報誌における編集後記の役割や書き方、そして実用的な例文まで幅広く紹介してきました。
編集後記は、情報を届けるためのページではなく、“人と人”をつなぐページです。
そこに正解やマニュアルはありません。
だからこそ、あなた自身の言葉で、感じたことや伝えたい思いを素直に綴ることが何よりも大切です。
| ポイント | 実践のヒント |
|---|---|
| 季節や行事に合わせた内容 | 読者と同じ空気感を共有できる |
| 感謝やエールの気持ち | 読者との信頼関係を築く |
| 読みやすい文章構成 | 短文+1テーマ1文を意識する |
| 自分らしい言葉 | 肩の力を抜いて“話しかけるように” |
もし迷ったら、このガイドにある構成と例文をベースに、少しずつ自分の言葉でアレンジしてみてください。
あなたの言葉が、誰かの心をあたためる——。
それが、編集後記というページのいちばんの魅力です。
次は、この記事全体をふまえて、読者の心に届くタイトルとリード文を作成します。